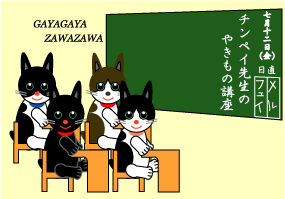
方丈庵の特別名誉講師、チンペイ先生が、やきものに関する質問になんとな〜く答えたり
唐突に歴史、技法の講議をしたりしちゃうスペシャルコーナーです。
みなさんも、やきものに関する疑問、質問がありましたら、どしどしメール下さいね!
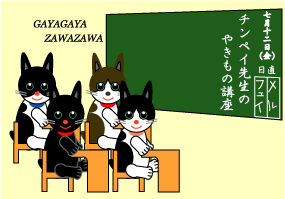
方丈庵の特別名誉講師、チンペイ先生が、やきものに関する質問になんとな〜く答えたり
唐突に歴史、技法の講議をしたりしちゃうスペシャルコーナーです。
みなさんも、やきものに関する疑問、質問がありましたら、どしどしメール下さいね!
やきものとは、ここでは陶磁器を指します。粘土を成形し、あるものは釉薬を施し、窯の中で高温で焼き上げた器、それがやきものです。
信楽焼、備前焼、有田焼、常滑焼、萩焼...。数えあげればきりがありませんが、日本各地にその生産地があります。○○焼という名前のほとんどが生産された場所の地名です。そして、それぞれが個性豊かなやきものを産出して来ました。
一言で粘土といっても、その成分は産出する場所により様々に違います。赤土の赤い色は酸化第二鉄=あかさびの色ですが、この酸化第二鉄やマンガン分など、酸化金属の割合が高いと黒褐色になり、少ないと淡い茶色、ほとんど含まれないと白色になります。
また、その他の成分、たとえば珪石という耐火度の高い成分が多いとか、土の粒子の細かさ、不純物の多少等によって、やきものとして完成した時の焼き上がりの色合い、肌合いに大きな影響がありますが、その成分が、それぞれの地方でかなりの違いがあります。
この、日本各地で違う原料の成分が、○○焼の特色に強く影響を与えています。
また、日本のやきものは、ほとんどがおおむかし、大陸系渡来人が技術指導をおこなって発祥しましたが、中国系渡来人が伝えた技術と、朝鮮系渡来人のそれとでは、ロクロ技術、装飾技法、築窯方法にかなりの相違があります。このいずれかをルーツとするかによっても、○○焼の持つ特性に影響が見られます。
その土地それぞれの特色ある原料を、その地方それぞれの技法で成形、装飾、焼成され、何百年もの間に洗練、進歩した独特のやきもの、それが○○焼と呼ばれるものです。ある地方の特産品であるやきもの、と云う言い方をしても良いかも知れません。
しかし、情報伝達手段の驚くべき進歩と、流通機構の発達により日本はおろか、世界各地の原料が手軽に手に入るようになった現在、○○焼が持つ特殊性は失われてしまったかに思えます。
事実、多くのやきもの産地がオートメーション化した工場による効率の良い大量生産の道を辿っている今、たとえば瀬戸のメーカーが作る製品と他の産地の製品と比べても、デザインの差こそあれ、そこにやきものとしての独自性は見出せません。実用陶器に限って言えば、日本中のやきもの技術が均一化されてしまいました。
しかし、ごく少数の人たちが、昔ながらのローテク技術で作陶を続けています。○○代○○左衛門さんとか、××代××兵衛さんとか名乗っているひとたちですが、彼等が一子相伝、門外不出、電気不要の何百年前と同じ技法でつくり出す伝統工芸を除いて、現代には○○焼と呼べるものは無くなってしまったと言っても過言では無いでしょう。
では方丈庵をはじめ、東京の陶芸教室で作っているやきものは、何と呼べばよいのでしょうか?
私はやはり、「やきもの」と呼ぶのが一番正しいと考えます。
やきものとはやきものの事であると云う、おかしな論理になってしまいましたが、これが結論です。
たとえ、備前や萩から原料を取り寄せ、窯の雰囲気や温度を工夫して焼き上げても、それが生み出される空間が(特にやきものの僻地である東京の)陶芸教室である以上、備前焼でも萩焼でもありません。
○○焼と云う伝統美の再現を夢見てにいかに模倣してみても、それが生み出された地域性、時代性の追体験が不可能である以上は、まがいものに終わってしまうからです。
○○焼に憧れて作陶を始めたと云うような方にとってはなんだか不愉快な話になってしまいましたが、私は、伝統への憧れを否定するわけでは無く、それもふまえた上で、自由に作陶を楽しんで戴きたい、と思います。
私は、私の仕事に対して極力陶芸と云う言葉を使わず、「やきもの」と呼ぶ事にしています。やきものと云う、ある意味で漠然として限定されない名称に自由性を感じるからです。
そして、趣味でやきものを楽しむ皆さんこそ、限定された地域、時代の特殊性に拘束されない、広い意味での「やきもの」を楽しんで戴きたいと願っています。
これも皆さんから非常によく尋ねられる質問です。
少し長くなりますが、素材的な陶器と磁器の違いと、日本におけるその歴史を考察してみたいと思います。
●やきものの分類
やきものを陶磁器、と称する事もありますが、これは陶器と磁器を総称した呼称です。この陶磁器を更に分類すると、次の4つのカテゴリーに分けられます。
○土器
○陶器
○せっ器(火偏に石と書きます)
○磁器
土器とは、縄文式、弥生式土器のような、釉薬を施さない、低火度焼成(1000℃未満)された為焼き締まっていない、吸水性のあるやきものの事を指します。園芸用の植木鉢も土器に入ります。
陶器は、広い意味ではやきもの全般を指しますが、狭義では吸水性のある素地に、釉薬を施したものを指します。
せっ噐とは、素地が完全に焼き締まって、吸水性が無いやきものの事です。多くは無釉です。
この3つのやきものを広義では陶器と総称しています。
陶器の生地の原料は山や田んぼから掘り起こして来た土です。
もとを正せば土は岩が熱水作用によって分解変質したものですが、それが河川など自然のちからによって流され篩われて、堆積されたた土を二次粘土といいます。
陶器の素地の原料はこの二次粘土です。これを乾燥させ篩いに掛けたり、水漉ししたりして粒子を揃えるなどの手間を掛けますが、本質的には陶器は、自然の中から採掘された原料をそのまま胚土とします。土が原料と云うことで、陶器には「土もの」という別称もあります。
これに対して磁器は、日本では陶石と云う白色の脆い岩を細かく粉砕したものを水で練って粘土状にしたもの、大陸や西洋ではカオリンと云う,白色の岩がその場所で土化したもの(これを一次粘土といいます)に長石、石灰、骨灰などをブレンドしたしたものを練り上げて胚土とした、いわば人造的なやきものです。石が原料と云うことで磁器のことを「石もの」と呼ぶこともあります。
高温で焼成すると表面がガラス化して透光性を帯び、高い硬度も持ちます。色は純白、釉薬の成分や焼成方法によっては青白色になり、吸水性は全くありません。
例外もありますが、土器、陶器、せっ器と磁器の特徴を表にすると、下図のようになります。
|
土器
|
陶器
|
せっ器
|
磁器
|
|
|
素地の色合い
|
有色
|
有色(または白色)
|
有色(または白色)
|
純白色
|
|
吸水性
|
○
|
○
|
×
|
×
|
|
透光性
|
×
|
×
|
×
|
○
|
|
釉薬の有無
|
×
|
○
|
×
|
○
|
|
焼成温度
|
600〜1000℃
|
900〜1250℃
|
1000〜1300℃
|
1250〜1380℃
|
|
代表的なやきもの
|
縄文式、弥生式土器
|
薩摩、唐津、萩など
|
備前、常滑朱泥など
|
有田、九谷、清水など
|
人類がはじめてやきものを作るようになったのは、諸説あるようですが、およそ紀元前1万2千〜5千年ぐらいだと云う事です。
火を発見し、食べ物を焼いて食するようになった人類は、焚火を燃やして原始的な竈を使用するようになりました。
その周りの土が固く焼けている事を知って、器を作る事を考え付いたと思われます。これが「土器」の起原です。
| 図ー1a | 図ー1b | 図ー1c | |||||
 |
 |
 |
|||||

| 図ー3a | 図ー3b | |||
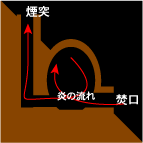 |
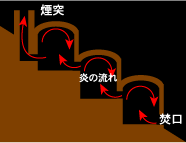 |
|||
●釉薬の発見
このような1000℃以上の高温による焼成の過程では、作品に降り掛かった燃料の灰が、土と融け合って光沢を持つ皮膜が生まれる事があります。
また、成分によっては、低火度では形を保っていても、高火度焼成すると、どろどろに溶けてガラスのように液状になる土もあります。
この経験から、やがて釉薬が作られるようになります。
始めの頃は、現代の焼締陶にもみられるような、自然降灰によるもの、耐火度の弱い土を素地表面に塗って水漏れ防止にしたものが主流であったと思われますが、やがて土石と灰を混合して、より光沢のある、美しい釉薬へと発展していったのでしょう。この前の項で述べたように、中国ではかなり昔から磁器の製法が発見されていたので、白い生地を活かした青磁釉などの宝石のような釉薬が生まれるようになります。
釉薬とは、粘土素地の表面に薄く溶け付いたガラス状の皮膜です。釉(ゆう)、釉薬(ゆうやく)、薬、釉(くすり)、上薬、上釉(うわぐすり)とも呼ばれます。
古代中国ではその光沢から「油」の字を当てていましたが、さんずいは水を表わすため、石偏に由と書くように変わり、さんずいに幼と書くようになったりしましたが、最終的に現在の、「彩」の偏と由を組み合わせて「釉」の字が出来たようです。
釉薬の役割としては、素地の吸水性の防止(水漏れを防ぐ)、素地の耐久性の強化、そして工芸品としての装飾性があげられます。
釉薬の原料やその配合について詳しく述べようとすると、それだけで分厚い本が1冊出来てしまうので、ここでは割愛しますが、釉薬の溶けを良くする媒溶原料(木灰、石灰などの灰類やソーダ類)、粘りを持たせる粘土質原料(長石、陶石、カオリンなどの土石類)、溶け過ぎを防ぐ、いわば骨組みになる珪酸質原料(珪石、ワラ灰など)色合いを美しくする為の着色材(酸化第二鉄、酸化コバルト、酸化銅などの酸化金属)を目的に応じ調合して作られます。
窯焚きの方法は、酸化炎で焼く酸化焼成(Oxidized Firing=O.F.)と、還元炎で焼く還元焼成(Reduced Firing=R.F.)に分けることが出来ます。酸化焼成とは、焼成中の炉内に充分酸素を送り込む方法、還元焼成とは、炉内に一酸化炭素を充満させる方法です。
窯の構造が未発達だった時代は、燃料が不完全燃焼するために、必然的に還元焼成されていました。やがて煙突の発達など構造的な進歩により、酸化焼成が可能になりました。還元焼成されていた須恵器の中で、偶然生まれた酸化焼成されたやきものが備前焼の始まりだという説があります。
この酸化焼成と還元焼成の違いを、概念的なガス窯を例に説明します。
この窯では簡略化するため、酸化第二鉄=Fe2O3を多く含んだ粘土で作った壷をひとつ焼くことにします。酸化第二鉄とは鉄の赤錆びのことです。やきもの以外の工芸品にも顔料として使用され、ベンガラと呼ばれているものです。焼成温度は1250℃としましょう。
ガス窯での焼成は、酸化還元共に300℃までは急激な温度上昇を避ける為、炎を不完全燃焼させて焼成、300℃からは効率良く温度をあげる為、完全燃焼させます。
この、炎の酸素量の調整はバーナーの空気調整リングで行います。
| 図-4a 酸化焼成 | 図-4b 還元焼成 | |||
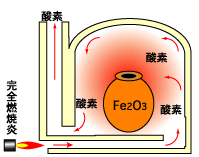 |
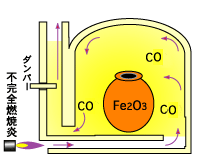 |
|||
酸化焼成の場合は、このまま1250℃まで完全燃焼させます。炉内の雰囲気は、煙突からの引きにより常に酸素(空気)が対流しているため、熱作用により粘土の組成は変化し、焼き締まりますが、酸化第二鉄という分子には変化は在りません。「酸化焼成」といっても、炉内の雰囲気を酸素で占めるようにしているだけで、化学的な酸化現象は起こりません。そのため焼成による劇的な変化は期待出来ませんが、安定した優しい色合いの作品が得られます(図-4a)。
これに対し、還元焼成では炉内温度が900℃〜980℃に達した時に、バーナーを不完全燃焼状態に戻します。さらに、煙突の途中についているダンパーという扉を閉めたり、図にはありませんが煙突の根元部分にあるドラフトと云う窓を少し開けて、煙突の引きを悪くしてやります。しばらくすると炉内の圧力がプラスに転じる為、窯に開けてある色見穴から10〜15cmぐらいの火ベロが出て来て、あたりに硫黄のような臭気が漂いはじめます。この時、窯の中の雰囲気は一酸化炭素=COが充満していますが、この一酸化炭素が酸化第二鉄の酸素原子をひとつ奪って二酸化炭素へ転じ、酸化第二鉄は酸素原子をひとつ失って、より純鉄に近い酸化第一鉄へ還元されます。このため壷の色は、酸化焼成では赤褐色に焼き上がるのに対し、還元焼成では鋼鉄のような黒褐色にあがります(図-4b)。
この現象の化学方程式は
Fe2O3+CO→2FeO+CO2
となります。
鉄は地球上では単体の原子としては希にしか存在せず、多くは酸素原子ひとつと結合し、FeO=酸化第一鉄として産出するのですが、空気中ではこれも不安定で、2つの酸化第一鉄分子がひとつの酸素原子と結合したFe2O3という状態へ酸化しようとする性質を持ちます。鉄製品がすぐ錆びてしまうのはこのためです。
この他の酸化金属、コバルト、鉛、錫、クローム、ニッケルなども勿論還元炎により変化しますが、最も劇的に変化するのは銅(Cu)でしょう。
織部釉は酸化銅や炭酸銅=緑青を着色材とした釉薬で、酸化焼成では緑色に発色しますが、還元焼成では銅本来のあかがね色に還元され、更に釉薬の成分によっては真紅、青紫色に発色することもあります。中国の辰砂(しんしゃ)、牛血紅(ぎゅうけっこう)、火炎青(かえんせい)などがそうです。
勿論、現実的には、粘土や釉薬に含まれる全ての酸化金属が思い通りに還元されるわけではありません。炎の状態や窯の構造に左右され、理想的な還元焼成は経験が必要です。
炉内の一酸化炭素の濃度を高い事を「強還元」状態と呼びますが、煙突の引きが悪いため、長い焼成時間が必要です。また、必要以上に一酸化炭素を充満させると「油煙がまく」と云って釉薬が黒ずんだりします。
目的温度の手前30〜50℃で還元状態を止めて、緩やかに酸化焼成へ戻す方法を「中性炎焼成(Neutral Firing=N.F.)」と呼びます。油煙防止や焼成時間の短縮、また「御本手」と呼ばれる化粧土に浮き出る緋色の半纏を求める場合は有効です。うまくいけば酸化と還元の「良いとこ取り」のような作品が得られます。
いずれにしても、各々特色のある焼成方法です。様々に試してみて自分の好みにあった焼成方法を見つけることが肝心だと思います。